連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第21回
こんにちは、森田です。
2018年は映画『万引き家族』がカンヌ映画祭でパルムドールを受賞したことで、改めて「疑似家族」に注目が集まっています。
10月20日にロードショー公開がはじまった映画『ごっこ』も、家族のあり方や親子の愛情を再考するには最適な作品です。

(C)小路啓之/集英社 (C)2017楽映舎/タイムズ イン/WAJA
今回は本作とそれに関連する漫画『ママゴト』を取りあげ、疑似家族の本質や人間を大人にする共同体の原理に、考察の目をむけてみたいと思います。
CONTENTS
映画『ごっこ』のあらすじ(熊澤尚人監督 2018)
早世した漫画家・小路啓之の同名マンガを『心が叫びたがってるんだ。』『ユリゴコロ』(2017)の熊澤尚人監督が映画化。
主演を務めるのは、『ポルノスター』(1998)や『HYSTERIC』(2000)、そして劇場版『新・ミナミの帝王』(2017)と着実に俳優としてのキャリアを積んできた千原ジュニアです。
まとめを先どりすると、本作のジュニアの演技は、芸人から映画人に転身した大先輩・ビートたけしを継ぐに足る実力をみせつけます。
その相手役は、5歳の娘「ヨヨ子」を演じた平尾菜々花。気が強くて、斜に構えていながらも無邪気さを持ちあわせ、しかも連れ去られて親子関係を築くという難役に挑みました。
そう、父親の城宮(ジュニア)はある日、向かいのアパートで傷だらけになっていたヨヨ子をさらって、自分の家に連れこんだのでした。
つまりは、誘拐です。
しかも、城宮には定職がなく、ほぼ引きこもりの状態。日がな一日、美少女フィギュアをつくっているところをみると、世間的には「オタク」と呼ばれる存在です。
そんな40歳手前の男性が、すなわちもっとも“親”から遠い場所から、「子ども」に、「大人」に、そして「自分」という存在に近づいてゆきます。
熊澤尚人監督が込めた想い 不寛容な社会へ
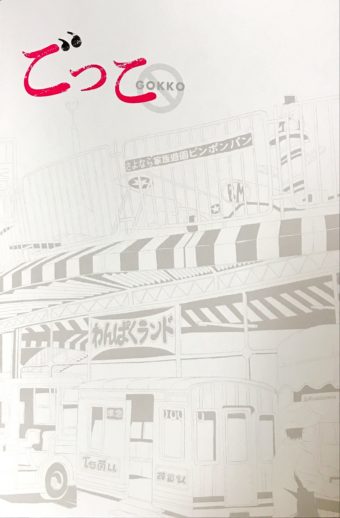
『ごっこ』公式パンフレット
“血縁ではない”という関係を描くにしても、多くの社会的スティグマ(否定的な烙印)を主人公に付し、これほどまでに親と子の距離を広くとっている理由。
監督が公式パンフレットに寄せたこの言葉が、理解の一助になります。
「私はかねてから、今の社会の不寛容さを題材にした作品をつくりたいと思っていました。世の中には生きるのがへたくそな人間が沢山います。上手く生きられない人が、自分より弱い人に出会った事で、弱い人をなんとか助けようとする。それがきっかけで、自分も前に進むことになり、人間的にも成長する」
“社会的な弱さ”には、やはり主題上の意味があるといえるでしょう。
この「不寛容さ」の一例が、作中で具体的に示されています。年金の不正受給です。
ニート同然の暮らしをしていた城宮に、子どもを養える経済力はありません。
そこで彼は実家の帽子屋に里帰りすることに決めるのですが、子どもをみて安心した父親からある“贈り物”を受けることに。
それが「年金」でした。父親は老人ホームに行くと偽ってみずから命を絶ち、死後の年金を息子に授けました。
この「自己犠牲=贈与」が、その後の城宮の行動にも影響を与えます。
『ごっこ』の原理「贈与と返礼」 マルセル・モースの『贈与論』から

『贈与論』(ちくま学芸文庫/2009)
ここでフランスの社会学者、マルセル・モース(1872~1950)がおこなった「贈与」についての研究を参照してみます。(引用はM.モース著・吉田禎吾、江川純一訳『贈与論』、ちくま学芸文庫、2009年より。)
モースによれば、人間社会は近代人が考えるような「奪いあい=否定的互酬性」の経済原則を超え、「贈与と返礼の義務」をもとに構築されているといいます。
「受け取った贈り物に対して、その返礼を義務づける法的経済的規則は何であるか。贈られた物に潜むどんな力が、受け取った人にその返礼をさせるのか」p.14
この目的のもと、マオリ族の調査などでわかったことは、贈り物に潜む力は「贈り物を受け取った者はお返しをせざるをえない」という「負債感情」に根ざしていることでした。
比喩的に言い換えると、贈り物には「贈与の霊」がつきまとい、もらい手はまた別の人に贈り物をして、その霊を移動させなければなりません。
それはまるでサッカーボールをパスするように人々のあいだを循環し、共同体の存続に必要な交流がうながされるというわけです。
映画『ごっこ』にも、この循環が確認できます。
城宮の父の“密葬”を手引きした友人(石橋蓮司)は、城宮のためではなく、父から受けた恩のためだと理由を明かします。
そして城宮は、その友人を介して父親からもらった年金を、他人のヨヨ子のために使います。
整理すると、城宮父=友人=城宮=ヨヨ子と、贈与の輪がつながっていくのが見えますね。
モースが見通した原理が、作中の現代社会にも貫いているのが確認できます。
なお成長したヨヨ子(清水富美加)は、自分を守るために罪を犯し、刑務所にいる城宮を救うべく、弁護士になることを志します。これもまた「返礼」のひとつでしょう。
『ごっこ』と『ママゴト』 漫画の比較から

(C)小路啓之/集英社 (C)2017楽映舎/タイムズ イン/WAJA
弱き者がより弱き者と出会い、疑似家族を形成するなかで、それぞれが大人になる。
小路啓之の『ごっこ』のほかに、同様の構図をもつ漫画を1作あげるとすれば、松田洋子の『ママゴト』(月間コミックビーム2010年~2012年連載)に匹敵するものはありません。
2016年には安藤サクラ主演で実写ドラマ化されましたが、奇しくも、両作品ともほぼ同時期に連載されていました。
場末のスナックのママ・恩地映子のもとに、旧友の滋子が大滋という5歳の子を連れて姿をあらわします。
滋子は借金取りに追われており、大滋を映子に預けて行方をくらますつもりでいました。
赤ちゃんを亡くした過去に縛られていた映子は、不安を感じながら大滋との共同生活を送るうちに、自分の過去を再構築してゆくことになります。
遊園地と疑似家族のはじまり 『ママゴト』より

『ママゴト』(ビームコミックス/2011)
『ごっこ』も『ママゴト』も、家族を「まねごと」ととらえていることは、言うまでもありません。
そしてどちらも、父親や母親にもっとも近づける場所として「遊園地」が用いられています。
『ママゴト』では、スナックの常連客からもらったチケットを利用し、映子は大滋をはじめての遊園地に連れていきます。
幼いころに母親が失踪してしまった映子も、一度も行ったことがありませんでした。
夢中になってさまざまなアトラクションを楽しむふたり。「鏡の迷路」に入り、映子はあるものを見つけます。
「一瞬、鏡に映った自分をお母ちゃんが立っとるんか思うた。お母ちゃんがおらんなってから、うちはずっと迷子みたいな気がしとったんよ。あん頃のお母ちゃんの歳になってきてわかったん。お母ちゃんも迷子じゃったんよな」ママゴト2巻 p.116
子どものころの映子は、ひとりで働く母親に迷惑をかけまいと、デパートの屋上で観覧車を目にしても「乗りたくない」と首をふっていました。
しかし、大滋と遊んで気づいたのは、「母も自分を楽しませたくて乗りたかったはずだ」という気持ち。
自分が楽しむよりも、大事なだれかに楽しんでもらうことのほうが、よっぽど楽しい。
その想いが交差するところに「家族」があるとすれば、互いに “演じあっている”といえるかもしれません。
逆にいえば、「信頼をよせて演じあえる場所」さえつくれれば、血縁もなにも関係なく、ひとつの家族になれるということです。
「疑似家族」の本質はここにあります。
その事実に思いあたった映子は、大滋と「両想い」でいられるかぎり、どこにいても家族であるという希望を胸に抱え、大滋を滋子のもとに帰す決断をします。
そうして、いつか公園でしていた「ママゴト」をふり返るのです。
「お母さんや子供になりきって、石や草でごはん作って、みんなほんとのつもりでやっとるけえど、本当のお母さんが本当のごはんができたら呼びに来るん。それが正しいママゴトの終わりかたじゃって思うたな」
「カラスもとっくにおらんまっ暗なとこでひとりママゴトしよった。誰も呼びに来んから。もううちは自分で終わらせられたけ。あの頃とは違う。もう大人になれたけ」(ママゴト3巻 p.196)
少女の映子は「本当のママ」を待ちつづけ、いつまでもママゴトを終わらせることができなかった。
しかし、大滋と出会った映子は、「本当の親子だってママゴトである」という認識を得て、自分で自分の物語を選べるようになりました。
遊園地と疑似家族のおわり 『ごっこ』より

(C)小路啓之/集英社 (C)2017楽映舎/タイムズ イン/WAJA
一方で『ごっこ』における遊園地のシーンは、別れの場面に使われます。
ヨヨ子の母親を殺した城宮は、ヨヨ子と一緒につかの間の旅にでます。その逃避行の最後に、閉園した遊園地にもぐりこむのです。
城宮を演じたジュニアは、そのときの様子をこのように顧みます。
「遊園地のシーンは、楽しそうに遊んでいるけれど、これで終わりだという微妙な空気が流れているような気がします。役としても自分としても終わりだという事を理解しながらも、お互いにそれは口に出してはいけないというような空気感。それが場面にマッチしています」(公式パンフレットより)
まさしく、映画をつくる現場もひとつの「家族ごっこ」といえます。
物語の進行順に撮られていった本作は、遊園地で2重の終わり(城宮とヨヨ子の関係、千原ジュニアと平尾菜々花の共演)を迎えました。
ここでの遊園地は「家族ごっこ」の場であると同時に「変身ごっこ」の場でもあります。
ヨヨ子は特撮番組が大好きな女の子。「パパやん」にヒーロー像を見いだしていたことは想像に難くありません。
父親からの「贈与」と子どもからの「期待」に応じ、城宮はそれまでの自分から「変身」しました。
しかしながら、実際の特撮ヒーローがそうであるように、それには制約・制限が設けられているのが常です。
遊園地といえばヒーローショー。遠くから鳴り響くパトカーのサイレンが、ふたりのショーの終了合図となりました。
ビートたけしを継ぐ者 千原ジュニア

(C)小路啓之/集英社 (C)2017楽映舎/タイムズ イン/WAJA
かつて『クレイマー、クレイマー』(ロバート・ベントン監督/1979年)は父親のワンオペ家事を描き、離婚大国・アメリカの実情を世にさらし、『タクシードライバー』(マーティン・スコセッシ監督/1974年)は孤独な青年が少女を守るためにとった凶行を社会に突きつけました。
映画『ごっこ』は、それらの要素が現代の日本社会に落としこまれている作品です。
純粋さと凶暴さ、優しさと孤独を一身に背負った千原ジュニアの存在感は見事というほかありません。
それには、ビートたけしが北野武になり替わろうとしていたころの勢いや肉体性に近いものがあります。
実際に刑務所でのラストシーンは、たけしが映画俳優として歩む道を決定づけた『戦場のメリークリスマス』(大島渚監督、1983)へのオマージュを意識せずにはいられません。
大学合格を決めたヨヨ子は、過去の記憶をたどって城宮との面会にのぞみます。
坊主頭の城宮は、最初は固く口を閉ざしていたものの、自分とヨヨ子とのあいだに愛情が結ばれていたことを再認識すると、目に涙をためて相好を崩します。
「パパやんつかまえた」
「鬼ごっこちゃうぞ」
ジュニアの顔を画面いっぱいに映しだすカメラ。そこで、映画は終わります。
まさに『戦メリ』の最後に坊主頭のたけしがみせた“あの笑顔”です。
かたちだけでなく、本作でたしかな演技をみせた千原ジュニアは、たけしの軌跡をなぞるように映画界で活躍していく可能性を秘めているでしょう。
【参考】坂本龍一×デヴィッド・ボウイ×ビートたけし映画『戦場のメリークリスマス』考察。3者の越境で自由と平和を示す|映画道シカミミ見聞録9



































