連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第19回
こんにちは、森田です。
いまや邦画の人気ジャンルに定着した「職業ドラマ」のなかでも、「お酒づくり」はとくに愛されているカテゴリーのひとつです。
日本酒でいえば、農大生が醸造所で研修する日々を描く『恋のしずく』(主演:川栄李奈)が10/20に公開を控えていますし、ウィスキーではすこし遡りますが連続ドラマ小説『マッサン』(2014年9月~2015年3月放送)が話題となりました。

(C)河合香織・小学館 (C)2018 Kart Entertainment Co., Ltd.
そして「ワインの映画」というと、10/20公開予定の『ウスケボーイズ』が一押しの作品です。
今回は、日本ワインの発展に努めてきた青年らの物語から、「ワイナリーの思想」ひいては「生きるための思想」を読みとっていきたいと思います。
CONTENTS
映画『ウスケボーイズ』のあらすじ(柿崎ゆうじ監督 2018)
河合香織のノンフィクション『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』(小学館、2010)を原作に、ワイン醸造家の麻井宇介(1930~2002)の薫陶を受けた3人の青年たちが、各々の「日本産ワイン」をつくるまでの過程を描きます。
その3人は岡村(渡辺大)、城山(出合正幸)、高山(内野謙太)といい、それぞれ原作の岡本英史、城戸亜紀人、曽我彰彦に該当。
彼らは1993年、山梨大学大学院の修士課程で出会い、他のメンバーたちと「ワイン友の会」を開きながら親交を深めた仲です。
卒業後、岡村は食品メーカーに就職するものの、ワインづくりのため山梨に理想の土地を求めて脱サラ。
城山は長野県のワイン会社で働きながら、婿入り先のぶどう畑で栽培をはじめ、やがて独立します。
学年が1つ下の高山は、長野の実家がワイナリーを経営しており、家族との交渉の末に自分の畑を持つように。
そんな彼らが、日本のワイン水準を飛躍的に高めた醸造家、麻井宇介(橋爪功)の教えを自分たちなりに実践していくのが、本作の核となっています。
日本のワインの黎明期 海外産の“国産”ワイン

(C)河合香織・小学館 (C)2018 Kart Entertainment Co., Ltd.
本筋の紹介に入る前に、「革命前」の日本ワインの状況を整理しておきます。
“日本産”のワインを飲んで、すぐに欧米と味が違うことに気づくとしたら、「甘い」という特徴ではないでしょうか。
海外では「ワイン用ぶどう」を用いるのに対し、日本では長らくマスカット・ベリーA、デラウェア、巨峰などの「生食用ぶどう」を利用することがほとんどでした。
しかも、濃縮果汁やバルクワイン(輸入ワイン)を混ぜて「国産」と表記していました。
“国産”でも原料は外国産。なんだかしっくりきませんね。
日本では「醸造した場所」で国産か否かを決めており、たとえ輸入原料に依存していても、国内で加工されていれば“日本産”となるのです。
麻井宇介が怒りにも近い感情を抱いていたのは、このいい加減な状況を見かねてのことでした。
また、海外のワインづくりは自分の畑でぶどうを栽培し、醸造まで一貫して行いますが、日本では農家にぶどう栽培を委託し、ワイナリーが買いとるという方式。
麻井はここを、「日本ワインには思想がない」と指摘しました。
そして、思想さえあれば、欧米の“銘醸地”に負けないワインを日本でもつくれることを説き、実際に長野県塩尻市で『シャトー・メルシャン 信州桔梗ヶ原メルロー』を生産することに成功するのです。
3人の思想の出発点

岡村、城山、高山の3人も、院生時代に「ワイン友の会」でワインを嗜んでいたころは、ワインといえばフランスであり、日本ワインなんて話にもならない、と考えていました。
しかし、「日本ワイン」と「フランスワイン」のブランドを隠してテイスティングをしてみたところ、10本中の2位に、麻井の『桔梗ヶ原メルロー』が選ばれたのです。
これを機に日本産ワインの可能性に気づいた彼らは、麻井宇介を招いた合宿を実施。
ここが、麻井との師弟関係のはじまり、“ウスケボーイズ”の出発点となります。
麻井からの問い=批評の姿勢とは?
憧れの先生にいいところをみせたいと、メンバーたちはこれまでの知識を総動員してワインを評価してみせます。
ここが悪い、あれが足りないなどと、口々に交わされる発言。麻井はこう言ってのけます。
「このワインの『良いところ』は? どうして否定的なコメントばかり言うのか?」
みな、評価することを「批判」することと勘違いしていました。
これは、なんの「批評」にも当てはまることです。
ダメ出しをすると、なにか偉いことを言ったような気持ちになります。
でもそれは、生産者(つくり手)が一番わかっていることです。
ほんとうに必要で、ほんとうに難しい言葉は、つくり手さえ気づかないような「良さ」をだれよりも早く、だれよりも正確に、本人や他者に伝える作業なのだろうと思います。
麻井はワインづくりにおいて、その姿勢を貫きました。
「問題は『人』である。気候や土壌の問題ではない」
「ワインを知るにはワインだけじゃダメ」
「まずは志において彼らと同じ場所に立つ」
このように叱咤激励をします。
一方、チャレンジ精神旺盛の高山が、自分の畑すべてにピノ・ノワール(ブルゴーニュ地方の代表的なブドウ品種)を植えようとしていることがわかると、うまくいかなった先達を顧みて、強い口調でひき止めました。
「みんなで失敗を共有してやっていかなければ、時間が無駄になってしまう」
いたずらに夢を語るのではなく、しっかりと現実を見据えたうえで、若者たちを導いていたことがよくわかります。
「かつて日本にもワイン用ぶどうを植えた人がいた。しかし、それまでの日本のワインに欠けていたのは『造り手の思想』だった。自分の頭で考えるのではなく、良いとされているワインを目指してひとつの方向を向いていたのだ。そこに麻井が残してくれたのは、技術でも知識でもなく、ワインを造るために最も大切な思想であった」(原作『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』小学館文庫、2018年、P216)
では、その「麻井の思想」をより詳しくみていきましょう。
麻井宇介の思想
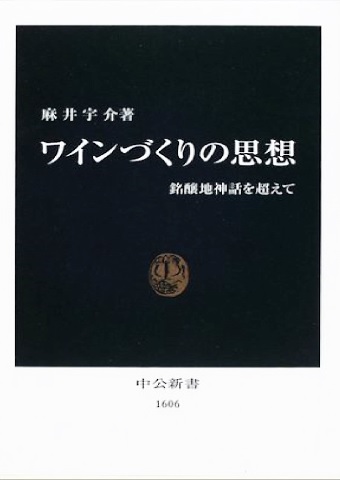
『ワインづくりの思想』(中公新書/2001)
麻井は何冊もの著書を残しており、原作によれば岡本(映画の岡村)は『ワインづくりの思想』(中公新書、2001)をすべて暗記するほど読みこんだといいます。
「ブドウ畑は、それぞれに個性を持つ。差異があるのは当りまえなのである。これを『風土の違い』と表現したあたりで、日本では銘醸地との差異が、追いつくことのできない宿命的な落差の意味を持つようになってしまった。(…)名づけて『宿命的風土論』という」
映画でも言及される「宿命的風土論」も、ここに登場。ワインむきの土地は決まっているという“神話”を崩しにかかります。
「真実は、良いワインとなるブドウを育てた場所を『恵まれた風土』といっているだけではないか。それは、神から与えられたのではなく、人間の手がつくり出したものであることを忘れてはならない」
要するに、結果論でしかない、と言っているわけです。根本には「人間」という存在があり、それだけが世界各地のワイン畑で共通しています。
ということは、ワインでみるべきは「風土の差」ではなく「思考の差」であり、作中の麻井の言葉でいえば「ワインになにを残したいのか。なにを排除したいのか」を考えてなくてはならない。
地理上の差異に応じて、人間のとるべき「選択肢」は変わってきますが、「選択がない」ことまで意味しません。
日本ではできないから輸入する、混ぜるでは、あまりにも思想がない、といってもいいでしょう。
それでは、どの方向に思想を持っていけばいいのか、あるいはより良い思想のためにはなにが必要か。
「ワイン造りには二種類ある。ひとつは目標とするワインがあり、それにぶどうを近づけていく方法。もうひとつは、まずぶどうありきで、それが自然にワインになっていくやり方である」(原作P206)
このことを、原作本をヒントに考えてみます。
原作ノンフィクション『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』

『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』(小学館文庫/2018)
映画には収録されなかったエピソードのひとつに、3人がシャンパーニュ、ブルゴーニュ、ボルドー、アメリカのナパバレーを約1カ月かけてめぐった卒業旅行の話があります。
ワインの“銘醸地”と呼ばれる場所には、どんな光が注ぎ、どんな人が作業しているのか、とにかく見てみたい。
その一心で醸造所のオーナーに直接会ってゆきます。そして、以下のことを学びました。
「世界最高級の白ワインを造るニーヨンは、実際に会ってみると鼠色の薄汚れた作業着を着て、気負いなく自然と向き合っていた」
「ワインの造り手は芸術家ではなく、農家だったのだ。作品を造っているのではなく、生活の一部として、その土地に根をおろして暮らし、ぶどうの育成を見守り続けてきている」(原作P56)
日本では優れたワインのつくり手は、まるで芸術家のように神格化されていた時代。
でも実際は、「生活」から生みだされているものでした。
つまり、「土地のぶどうありきで、それが自然にワインになっていくやり方」のほうです。
こう聞くと、“やっぱり土地の宿命があるのではないか”と思われるかもしれませんが、それならば「日本国内の土壌で育ったぶどうが、自然にワインになる方法がある」という考えもできるはず。
「ワインづくりは農業である」という基本に立ちかえり、3人のうちとくに岡村(岡本)は、亜硫酸無添加の栽培にたどり着きます。
「自然派なんて言葉さえ知らなかった。自分の内面を掘っていったら、気がついたらこういう風になっていた」(原作P20)
岡村は麻井から「だれかの真似をするな」と言われつづけてきました。
となると、周囲の自然を観察し、自分を見つめる方向に意識がむかうのも当然でしょう。
そのために、離婚も経験します。あまりにも妥協なく、修道士のように「生活」をしたがゆえに。
原作の曽我も、映画の高山とは違い、妻から「ワインをとるか、私をとるか」を迫られ別れを決断しています。
それほどに、「ワインづくりを生活にする」のは大変なことだったのです。
ただ、婿入りした城山(城戸)だけが、どうにか夫婦生活も維持することができました。ときには零下15度の作業をともにしながら。
「そんな寒さの中で、妻も一緒に畑に立ち、自分が切った枝を取り除いていく作業を分担してくれた」
「そうして眠っていた木が目覚める三月末。剪定された枝の切り口から、透明な液体が一斉にしたたり落ちる。これは『ぶどうの涙』と呼ばれて、化粧水にもなるほどぬるりとしたものなのだが、しかし夜温の低い城戸の畑では朝起きると、その涙が凍っている光景がしばしば見られた」(原作P121)
映画『ぶどうのなみだ』(三島有紀子監督 2014)
春の訪れを告げるこの「ぶどうの涙」を冠した映画があります。
北海道の空知を舞台にした本作は、主演の大泉洋がピノ・ノワールの栽培を手がける「ワイン映画」です。
先述したように、この品種によるワインづくりは日本においてはとても厳しいものですから、基本的にはファンタジー映画とみるべきでしょう。
その一方、かつての炭鉱の町で「黒いダイヤ」と呼ばれるピノ・ノワールを育てようとすることは、ひとつの「再生の物語」としてとらえることができます。
「ぶどうとして一度死んで、ワインとして生まれ変わる」
作中にはこんな台詞がはさまれ、大泉洋は「ぶどうの涙」をこう言って聞かせます。
「ぶどうの木は冬のあいだ、雪の下でひっそり眠っているんだ。でも春になると、雪解け水をいっぱい吸い上げて、小さな枝から、一滴の水を落とす」
『ウスケボーイズ』でさまざまな挫折を経験した3人も、「ぶどうの涙」は「泣いて目覚める」ことの象徴に受け止められるのではないでしょうか。
3人が見つけたそれぞれの思想

(C)河合香織・小学館 (C)2018 Kart Entertainment Co., Ltd.
彼らがワインづくりに取り組んである程度の時を経た2002年、末期がんにおかされた麻井を囲んでのワイン会が催されました。
それぞれが生産したワインをテイスティングした麻井は、三者三様の評価を与えます。
当時、農園に勤めていた城山には、
「これは面白いね。このワインには果実味がある」
と手放しで褒め、実家のワイナリーにワイン用ぶどうを植えた高山には、
「あと1年ぶどうの育成を見たら、変わると思いますよ」
と期待をかけます。しかし、会社を辞め、自分で開墾して畑をはじめた岡村には、こう言い残しました。
「自分の頭で考えなさい。海外ふくめ、誰かの真似をしなくていいんだから」
麻井はつぎの年のワインを口にすることなく、この世を去ってゆきました。
城山の思想=“理想”とワインへのアプローチ
その後、精進を重ねた3人のワインは、発売と同時に売りきれるほどの人気を博すようになります。
しかしながら、おなじ麻井の教えを肝に銘じていても、彼らが見つけた「ワインのつくり方=自分の思想」はそれぞれに異なるものでした。
原作の城戸を踏まえると、城山は「自然にまかせるのではなく、ぶどうやワインに積極的にアプローチして、自分が理想とするワインに導いてやることが造り手の仕事」だと理解。
品種によって理想のアルコール度数があるため、それに合致するよう必要に応じて補糖もおこないます。
高山の思想=“偶然”とビオロジック栽培
高山はある“出来事”がきっかけで、自分の思想を紡ぐにいたります。
自信をもって管理していたぶどう畑が、ある日、雹に降られて壊滅的な被害を受けてしまいました。
「もう今年の収穫は無理だ」と諦め、あとは殺虫剤も撒かず、薬も与えず放っておいたのですが、収穫の時期にはそれでも2割のぶどうが房をつけていたのです。
しかも、いつになく出来が良い。
ここから、農薬や防かび剤、そして化学肥料を使わない「ビオロジック栽培」への道を発見します。
またこれは、人生観にも多大な影響を与えたようです。
「もし収量が減ってしまっても、『ぶどうは取れませんでした』と謝ればいいだけだ。(…)ちょっとくらい虫に食べられてもいい。収穫が減ったっていい。病気にやられたっていいんだ」(原作P183)
そう、なにが起きても命まではとられない。その開き直りが、活路を見いだしました。
岡村の思想=“失敗”とぶどうまかせ
岡村は高山の思想をより徹底したかたちで「自然」を求めるようになりました。
酸化防止のための亜硫酸も入れません。
これには、自分が失敗したと思ったワインを「おいしい」と言ってくれた人々の存在が影響していると推察できます。
「ワイン造りは何かを選び出す作業ではなく、受け入れる作業なのだ。『良いワイン』かどうかなんて人間が決めるものではない。『良い人間』なんていないように。自然に生まれてきたものには良い悪いはなく、あるのは個性だけなのだ」(原作P209)
「自分がつくる」ではなくて「ぶどうが育つ」。そのための膨大な手間は惜しまない。
エゴを捨て、ありのままを受け入れる姿勢が、逆説的に「妥協のないワインづくり」と評されるように。
じつに不思議ですね。自分を手放すことが、自分自身にもっとも近づく方法であったわけです。
まとめ 思想はひとりではつくれない

麻井の教えを受け、岡村、城山、高山の3人がそれぞれに開花させた「ワイン=思想」は、互いが互いを参照するように育まれてきました。
自分の姿を見るには「鏡」が必要なように、自分の立ち位置を知るには「他者」が不可欠です。
最後のワイン会において、麻井は以下を「一番言いたいこと」に掲げていました。
「先にいろんなことが積み重ねられていてそれを受け継いでいくよりは、なんだか行き止まりを感じている、それを俺たちが切り開こうという方がはるかに面白いと思うんです」
「ところがひとりひとり頑張るにはその力の限界があるはずです。だから皆さん力をあわせて日本のワイン造りというのを前に進めていって欲しいと思うのです」
個人が「個」として立つために、ワインがひとつの「ブランド」を持つために「共同性」が求められる。
これはどの思想、どの仕事にも、敷衍できる考えでしょう。
麻井の教え子たちは、そのことを胸に刻むかのように、自分たちをイタリアの銘醸地、バローロを変革した仲間の「バローロボーイズ」になぞらえ、「ウスケボーイズ」と名乗るようになりました。



































