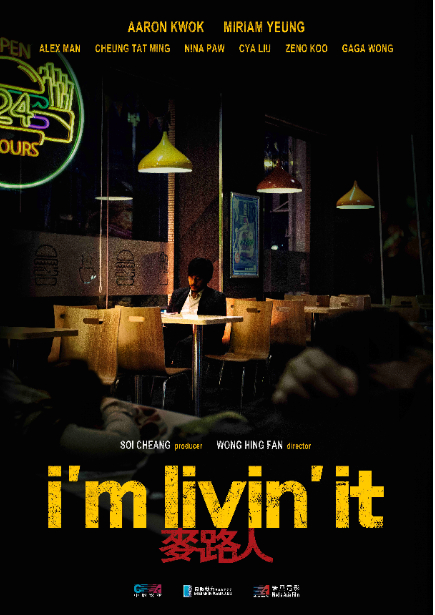第32回東京国際映画祭・アジアの未来『モーテル・アカシア』
2019年にて32回目を迎える東京国際映画祭。令和初となる本映画祭が2019年10月28日(月)に開会され、11月5日(火)までの10日間をかけて開催されました。

(C)Cinemarche
本映画祭の「アジアの未来」部門は、アジアで活躍する新鋭監督たちによる作品を対象とし、「作品賞」と「国際交流基金アジアセンター特別賞」(監督賞に相当)を目指して競い合います。
その一本として、マレーシアのブラッドリー・リュウ監督によるホラー映画『モーテル・アカシア』が上映されました。
CONTENTS
映画『モーテル・アカシア』の作品情報
【上映】
2019年(フィリピン・スロベニア・マレーシア・シンガポール・台湾・タイ合作)
【英題】
Motel Acacia
【監督】
ブラッドリー・リュウ
【キャスト】
JC・サントス、ヤン・ベイヴート、ニコラス・サプットゥラ、アゴット・イシドロ、ヴィタヤ・バンスリンガム
【作品概要】
父の遺した雪山のモーテルに出没するモンスターと対決する息子の奮闘を描いたホラー作品。
監督は本作で長編2作目となるマレーシアの新鋭ブラッドリー・リュウが担当、その他にもインドネシアのニコラス・サップトゥラをはじめ、多国籍のキャスト・スタッフが名を連ねています。
ブラッドリー・リュウ監督のプロフィール

(C)Cinemarche
1969年生まれ、マレーシア出身。
フィリピンを拠点に活動し、2016年にフィリピン・ロック界のレジェンドであるペペ・スミスを描いた映画『墓場にて唄う』で監督デビュー。同作はヴェネチア映画祭批判化週間でプレミア上映されました。
また、釜山国際映画祭のアジア・フィルム・アカデミーにも参加しています。
映画『モーテル・アカシア』のあらすじ

(C)Picture Tree International
雪のある日、フィリピン人のJCはしばらく疎遠となっていた父親と一人の不法移民者を車に乗せて雪道を走っていました。彼らがたどり着いたのは、山奥にある一軒のモーテル。
父からモーテルの経営を引き継ぐように言われていたJCですが、父は不法滞在者を欺き、ある一つの部屋へと連れ込みます。
何も知らず部屋に入り、室内に置かれたベッドの形をした石碑に横たわる不法移民。次の瞬間、彼はモンスターの餌食となってしまいます。
引き継ぐ仕事が何なのかを知り驚くJC。そんな彼に父は一つだけ忠告します、この部屋に「女性は入れるな」と。
そして次の生贄を得るために、再び車で雪の中を行く二人。しかし仕事を拒絶しようとするJCによって車が転倒し、事態は思わぬ方向に進んでいくのでした。
映画『モーテル・アカシア』の感想と評価

(C)Picture Tree International
本格的モンスター・ホラーといった趣の作品で、従来の名作ホラーを徹底的に研究しつくした感もあります。Q&Aでもブラッドリー・リュウ監督がコメントされているとおり、クリーチャーの登場シーンはホラーファン、特撮ファンとしてもかなり見ごたえがあるものとなっています。
しかしながら、“怖い”と思わせるスタートとは裏腹に、物語終盤には切なさを感じさせます。惨劇の餌食となった不法移民、子供を育てるために仕方なくこの仕事に手を染める女性など、登場人物の多くが社会から追い詰められた存在であるがゆえにです。
植物をモチーフとしたモンスターについても、画から伝わるショッキングなビジュアルとは逆に、“このモンスターもまた、世界から追い詰められてしまった存在なのではないか”と再考させられます。
いわゆる「B級ホラー」といわれる作品であれば、こういった一つ一つの要素に対するバックグラウンドはもっと薄く描かれる、あるいは全く描かれることなく、「恐怖の瞬間をいかに怖く見せるか?」に集中するところでしょう。
対してこの作品は、登場する人物たちそれぞれにバックグラウンドに深く関わる描写がなされています。
Q&Aでブラッドリー監督もコメントされていますが、本作では登場人物たちの観客の目が届かないところでの行動、映画を観ただけでは不確かな部分が要所にちりばめています。
たとえば主人公のJCにしても、父親とは明らかに違う人種であり、「どのような経緯で“親子”になったのか?」など疑問を抱く点が多々あります。
劇中における伏線はもちろん、場面ごとに起きる出来事をもたらしたのはそれぞれ誰なのか、登場人物たちのセリフ内でしか登場しない組織名の正体など、多くの疑問を掻き立てられたまま物語はエンディングを迎えます。
それは脚本としてストーリーを進めつつも、“解けることのない謎”を敢えて物語の中に作り出そうとしたブラッドリー監督の試みといえます。
モンスターホラーのテイストを存分に味あわせながらも、登場する人物一人ひとりに強く惹かれ、想像力を掻き立てられる作品となっています。
上映後のブラッドリー・リュウ監督 Q&A
第32回東京国際映画祭の開催期間中に行われたQ&Aイベントでは、ブラッドリー・リュウ監督が主演のJC・サントスらとともに登壇。
映画『モーテル・アカシア』に関する様々な質問に答えました。

(C)Cinemarche
──CGを使わなかった理由をお聞かせください。
ブラッドリー・リュウ(以下、ブラッドリー):これは全く意図的だったんですね。とにかくカメラに写るものは、そこに実際にあるものにしたいということ、それが私のこの撮影に当たってのこだわりでした。
プロダクション・デザインの二人は大変文句をつけて機嫌がよくなかったです(笑)。でもとにかく全くコンピューターエフェクトを使わず、すべて実際のものを作りたい、いわゆる80年代のいわゆるジョン・カーペンター監督の作品を彷彿させるようなアナログ式のものにしたいと思っていました。
まずグリーンスクリーンの前でテニスボールなどを持たせて映画の俳優に演技をさせても、なかなか真実味のあるものを引き出せないんじゃないかと思うんです。その意味では実際ものがあると俳優も演じやすいと考えました。
また私は現実的なものを求め続けたいと思っていました。80年代から90年代半ばの映像で使われた技術というのは、徐々に失われていく傾向にあります。
たとえばマットペインティングと呼ばれる技術は、最近では全部コンピューターで描けてしまいますから、なかなか使用される作品もありません。実際のモデル、模型を作るという技術なども失われつつあります。
今回はそんな状況に対して、すべてこだわって作り上げました。たとえばプールのシーンで、天井や壁に画が描かれていました、あれは大道具さんに手書きで、全部で4日間かけて描いてもらいました(笑)。
ブラッドリー・リュウ監督

(C)Cinemarche
──中盤、モンスターの恐怖から人々が脱出を試みる中で、脱出手段となる車に妨害工作が施されていたために「だれがやったのか」と揉めるシーンがあります。劇中では語られていないその犯人を、監督ご自身はご存知でしょうか?
ブラッドリー:だれがやったんでしょうね(笑)。「だれがやったか」と聞かれると、正直なところ困ってしまいます。そういうことを説明するのは、本来好きじゃないので。
普通は映画というと、観客が主人公の行動をずっと見届けつつも、「これが物語の真実だな」とちょっと安心感を抱きながら物語を追っていかれることでしょう。ですが今回の作品で、私はそれをしたくなかったんです。
つまり、JCがやっていることがすべてじゃない。「敢えてお客さんが見えないところで、JCがなにかいろいろ企んでいる」というような、観客にもたらされる不安感じみたものも描きたいと考えました。「見えていないところで、彼はほかのことをやっているかも」と観客に思っていただきたかったんです。
映画冒頭のJCはどちらかというとイノセントでとても純真な青年であり、お父さんがやっていることに反対しているんですが、お父さんがいなくなり「自分がこのモーテルをやっていかなければいけない」と思ったとき、責任感や生き延びていくための様々な感情を頭の中に抱いたと思うんです。
そして、あたかもお父さんの性質や資質がが彼の中に宿り、少しずつ見えてきます。その中で、彼が他の人にわからないところ、観客にも知られないところでいろいろなことをやっていると、そんな設定を実際に考えて物語を進めました。
主人公を演じたJC・サントスさん

(C)Cinemarche
──この作品に込めた思いを、改めてお聞かせいただければと思います。
ブラッドリー:実は昨日も、チームのみんなにこの映画に対する思い入れを話していたんです。
やはり映画人として、いわゆる社会に対する警鐘みたいなものを鳴らしたいと考えていました。
今、世の中ではいろんな不合理なもの、目を背けたくなるものがたくさんあるけど、多くの人たちはそれに目を背けています。何か行動に移そうとしてもなかなかできないし、やらないでいるということが多いと思います。ですが、そういった不合理な社会状況を無視していられない状況へと至っているとも思っています。
そこで私たちがアーティストとして、映画人としてなにができるかといえば、やはり映画を作ることしかできません。
ですがその映画をきっかけに、一人でも多くの人がなにかを行動に移したり、隣にいる人を気に掛けたりしてくだされば、そこからいろんな運動が始まっていくと思います。この映画も、そんな思いが形になればと思って作り上げました。
まとめ

(C)Cinemarche
ブラッドリー監督があくまで“映像のリアリティー”にこだわり作り上げた本作。映像による臨場感と恐怖感に溢れる描写だけでなく、観る者の感性に働きかける仕掛けも含まれており、ホラー作品として深みのある作品として仕上がっています。
その一方で、“現代の不合理性”というものを改めて考えさせられる作品にもなっています。観客は劇中における普通に考えれば不合理的な展開や描写に対し、それらの不合理が社会的な問題として現実に蔓延っているという事実に気づかされるからです。
そして映画の最後では、「“現代の不合理性”を描いた作品」として決して煮え切ることのない、恐怖の瞬間の後始末だけでは終わらないメッセージを観る者に投げかけているのです。