連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第12回

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会
こんにちは、森田です。
例によってこの夏にも多くのアニメ映画が公開されました。
そのなかで、わたしがとくに注目したのは『ペンギン・ハイウェイ』。
森見登美彦の日本SF大賞受賞作を映画化した本作は、ストーリー上の謎とあいまって鑑賞者にさまざまな見方を許し、その多義性からネットでも賛否両論を呼んでいます。
「賛」とするのは「おもしろい」とみる立場で、主人公の子どもがお姉さんという不思議な存在を通して“大人の階段”をのぼる物語として、受け止められています。
一方で「否」ととらえるのは「わからない」と感じる立場で、一連の出来事に対する説明が不足していて、またお姉さんもただの“都合のいい存在”にしか描かれていないと、すこし不満なようです。
実際にほとんどのレビューは「アオヤマ君の世界」を追ったものばかり。
そこで今回は、「お姉さんの世界」から物語の主題を考察し、広がりつつある謎を追求してみたいと思います。
CONTENTS
映画『ペンギン・ハイウェイ』のあらすじ
(石田祐康監督、2018)
主人公のアオヤマ君(声:北香那)は、日々、世界について知ったことや学んだものをノートに記録している小学4年生。
気になったことはすべて研究対象にするアオヤマ君にとって、目下いちばんの謎は、大きな胸を持つ歯科医院のお姉さん(声:蒼井優)の存在でした。
「ぼくはなぜお姉さんの顔をじっと見ているとうれしい感じがするのだろうか。そして、ぼくがうれしく思うお姉さんの顔がなぜ遺伝子によって何もかも完璧に作られて今そこにあるのだろう、ということがぼくは知りたかったのである」
要するにお姉さんのことが好きなんですね。でもその「好き」が「恋心」だと自覚するまでにはいたっていない。
本作を一言でいえば、「大人の女性」に抱く「不思議な感情」が「不思議な現象」として町に起こるSFで、「世の中にはどうにもならないこともある」と、子どもが象徴的に成長していくファンタジーです。
その現象の最たるものが、お姉さんからペンギンが生まれること。
アオヤマ君が大人になるために必要な過程は、「他者=お姉さん=説明のつかないもの」との出会いですから、「ペンギン」が出現する理由や「海」と名づけられた時空の裂け目の意味が、“論理的”に明かされることはありません。
これが「わからない」とする感想の背景にあります。
また子ども目線で世界がつくられているため、お姉さんの女性性を端的に示すものが「大きな胸」であるという、身もふたもない設定になっています。
これが「女性を道具のように都合よく描いている」とする批判のひとつです。
なるほど、アオアマ君はなんどお姉さんの胸に目を奪われていたことでしょうか。
アオヤマ君と“胸”の関係
メラニー・クライン「良い乳房と悪い乳房」論より
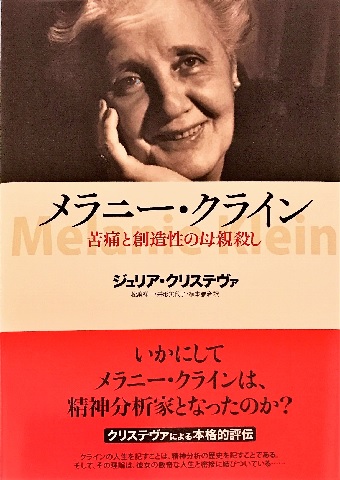
『メラニー・クライン』(作品社/2012)
物語の次元を超えて、あらゆる事物や関係に意味を見いだすのが考察ですので、ここで児童分析を専門とした精神分析家、メラニー・クライン(1882~1960)の理論を紹介します。
クラインは乳幼児期の“こどもの世界”をこのように考えました。
子どもが最初に出会う他者、母親。
その乳房を口にふくむとき、満足の体験と結びついた「良い対象=良い乳房」と、不満を与える「悪い対象=悪い乳房」を別々に形成しているのではないか。
この対象との関係のなかで、子どもは「良い乳房」も「悪い乳房」も母親の一部であるということを葛藤しながら認識していき、徐々に統一していく、というものです。
もちろんアオヤマ君はもっと大きい児童です。
しかし、日ごろから「良い対象/悪い対象=満足/不満足」の二項対立でわける癖がついているため、その内的世界にせまるには援用できる気がします。
つまりお姉さんの「胸」とは、女性性の象徴であるばかりではなく、「自分にとってどういうものかを認識しかねる存在」であり、その統一の過程で自己認識の破れが生じ、「海」という異界への入り口が開いた。そうは言えないでしょうか。
お姉さんと“神さま”の関係:宗教の代理としてのSF

『ペンギン・ハイウェイ』(角川文庫/2012)
このままお姉さんの表層的なイメージを覆していきましょう。
彼女は歯科医院で仕事をしている以外に、どんな日常を送っているのかが映画ではよくわかりません。
お姉さんがアオヤマ君の内的イメージで生きる存在であれば、彼の想像力の限界に縛られているからといえるでしょうが、原作を読むとまた違った面がみえてきます。
アニメでは消えた「教会」の存在
映画は映画内で分析すべきという意見もあるでしょう。
しかしながら、原作には尺の関係で泣く泣く削らざるをえなかった場面もあるでしょうし、その脚色から映画に込められた意味もおのずと判明してくることと思います。
原作との比較は映画の読みを深くするという観点から、お姉さんの大事な要素を取りあげます。
お姉さんは、教会に足しげく通っていました。
「並木道を歩きながら、お姉さんはもう教会にいるのだろうかと考えた。お姉さんはカモノハシ公園のとなりにある小さな教会へ通っているからだ」 原作小説P29
「日曜日の朝にはミサをしている。お姉さんがその教会に通っていることをぼくは知っている」P63
彼女が信仰を持っていたとなると、“都合のいい存在”から一歩抜けだします。信仰ほど、深く人間の内面にかかわるものはありません。
「学校には行かないと叱られます。教会は行かないと叱られますか?」
「そんなことないよ。私が勝手に行ってるだけだしね」
「お姉さんは神様が存在すると思いますか?」
「さあ、どうかしらん?」P140
また、お姉さんの故郷である海辺の町には、もっと立派な教会があったといいます。
「ぼくは海辺の街の朝のことを想像した。お姉さんの生まれた家は海が見晴らせる高台にあって、蔦のからまった古い家なのだそうだ。そこにはお姉さんのお父さんとお母さんが二人で暮らしていて、いつも潮の匂いのする風が吹いていて、となりの坂道をのぼった先には古い教会がある」P298
かなり具体的なイメージです。“胸“という部分対象からはだいぶ広がってきました。
なぜ人は神を信じるのでしょうか。
人の数だけそれぞれの理由はあると思いますが、大前提として「この世界には人知の及ばないことがある」といった認識を共有しているはずです。そのうえで、苦しみや悲しみなどの個別の問題が繰り広げられている。
「お姉さんは苦しさから逃れるために、ジャバウォックたちを作った。そのかわり、ぼくらの世界のこわれた部分は大きくなっていく」P354
アオヤマ君はそう考えました。ジャバウォックとは、ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』にでてくる架空の生物です。
その気味の悪い生物は、ペンギンたちを捕食してしまいます。
さきほどのクラインの論とあわせれば、お姉さんは「良い対象=ペンギン」も「悪い対象=ジャバウォック」も「ぼく」に与えてくる存在。
アオヤマ君の心理的な葛藤は、 その認識で“世界のこわれた部分”が大きくなることに示されています。
そしてお姉さんの苦しみの根源は、つきつめれば、ここにあります。
「アオヤマ君、私はなぜ生まれてきたのだろう?」
「わかりません」
「君は自分がなぜ生まれてきたのか知ってる?」P371
日本のSFが担ってきた機能
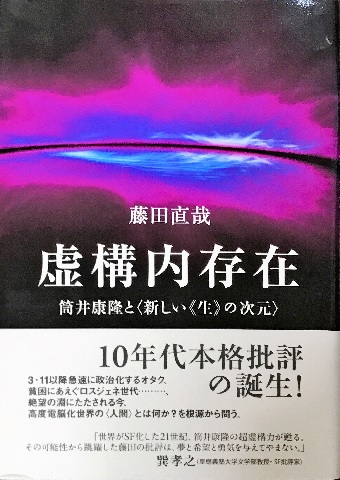
『虚構内存在』(作品社/2013)
ついに生まれた理由や存在意義を疑いはじめたお姉さん。
「良い悪い」でとらえきれない対象のいちばんは、「生死」であることに違いありません。
日本映画大学で講師を務める文芸評論家の藤田直哉さんは、「日本SFは宗教の代理として機能してきた」と言います。
敗戦後の日本は心理的な傷を覆い隠すかのごとく科学技術の道をつき進んできました。
当然、次第に「技術と人間の関係」が問われるようになります。
自分はどこから来て、なぜ生きて、どこに向かうのか。
そういった問題系は海外であれば「宗教」が受け皿になるわけですが、日本の場合はSFが虚構をもって存在の問いを先鋭化させ、心理的には宗教の代理を担ってきたということです。
『ペンギン・ハイウェイ』もSFに属すものとして、その流れをくんでいることは明らかでしょう。
「海辺のカフェ」と「海辺のカフカ」
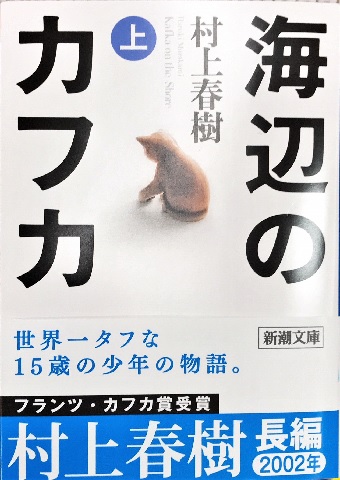
『海辺のカフカ』(新潮文庫/2005)
「自らの存在への問い」が、“子ども”と“お姉さん”のあいだで展開される物語のひとつに、村上春樹の小説『海辺のカフカ』(2002)があります。
「世界一タフな15歳の少年の物語」と銘打たれた本作は、家出をした「僕」が不思議な世界を行き来しながら少しずつ成長していく物語で、アオヤマ君がみる世界と同様に、いやそれ以上に「謎」に満ちあふれています。
「僕」は放浪先の町の図書館で「佐伯さん」と名乗る女性に出会います。
彼女は若いときに「海辺のカフカ」という曲を大ヒットさせた過去を持っていて、「僕」はそれを聴いてこんな印象を抱きます。
「不条理の波打ちぎわをさまよっているひとりぼっちの魂。たぶんそれがカフカという言葉の意味するものだ」P485(上巻)
そしてなんと、お互いの“魂”を救うために「僕」は佐伯さんと関係を持ちたいと言いだすのです。
「いずれにせよあなたは、あなたの仮説は、ずいぶん遠くの的を狙って石を投げている。そのことはわかっているわよね?」
僕はうなずく。
「わかっています。でもメタファーをとおせばその距離はずっと短くなります」P142(下巻)
その後は割愛しますが、「少年とお姉さんが、メタファーに満ちた不思議な世界で、心を救いあっていく」という筋書きは、まさしく『ペンギン・ハイウェイ』にも通じているのが、おわかりいただけるでしょう。
映画では「海辺のカフカ」ならぬ「海辺のカフェ」が、ふたりが心を通わす重要な場となっています。
チェスをしたり、町に降りかかった問題を解きあいながら交流を重ねていくのですが、最後、「お姉さんは人間ではない」と知ったアオヤマ君が、彼女と別れる場所でもあります。
「それじゃあ、そろそろサヨナラね」
お姉さんはぼくから離れて立ち上がり、歩きだした。
ぼくも立ち上がろうとしたけれど、お姉さんは「海辺のカフェ」の入り口でふりかえって、「君はここにいなさい」と言った。
「危ないかもしれないから」P373
一方で、こちらは『海辺のカフカ』で「僕」と佐伯さんが別れる場面です。
「さよなら、田村カフカくん」と佐伯さんは言う。「もとの場所に戻って、そして生きつづけなさい」
「佐伯さん」と僕は言う。
「なあに?」
「僕には生きるということの意味がよくわからないんだ」P472(下巻)
アオヤマ君も「僕」も、片や「海」の向こうの異世界から、片や森の奥の異世界から、現実世界に戻ってきました。
“世界の果て”へとつながる「ペンギン・ハイウェイ」

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会
ともに少年たちは「世界の不思議さ=不条理さ」を学んで、大人になる第一歩を踏みだしました。
お姉さんと別れたアオヤマ君に、父親はその学びをまとめるかのように声をかけます。
「そこにも世界の果てがあるね」と父は言った。
「どこ?」
「おまえが理不尽だと思うことさ。おまえにはどうにもできないのだから」
「ぼくは世界の果てに興味があるよ。でもたいへんやっかいだね」
「それでも、みんな世界の果てを見なくてはならない」P380
そして、カフカ少年の内なる声も、似たことを本人に告げるのです。
「たとえ世界の縁までいっても、君はそんな時間から逃れることはできないだろう。でも、もしそうだとしても、君はやはり世界の縁まで行かないわけにはいかない。世界の縁まで行かないことにはできないことだってあるのだから」P527(下巻)
「知」から「信仰」を獲得したアオヤマ君
内的な死や理不尽さを通過することで、それまで整然と見えていた二項対立の世界に変化があらわれます。
論理では推し量ることのできない物事が、世の中にはある。とくに人を好きになるような感情には。
「ぼくは世界の果てに向かって、たいへん速く走るだろう。(…)世界の果てに通じている道はペンギン・ハイウェイである。その道をたどっていけば、もう一度お姉さんに会うことができるとぼくは信じるものだ。これは仮説ではない。個人的な信念である」
ここまでお読みいただければわかるかと思いますが、理不尽さを経験したアオヤマ君は、もうお姉さんと会えないことを“論理的”には知っています。
それでも「会うことはできる」と“個人的な信念”として信じることに決めたのです。
あたかもお姉さんの信仰心が、アオヤマ君に移ったかのように。
つぎにアオヤマ君がお姉さんと会うときは、もう“胸”をまじまじとみることないでしょう。
お姉さんは喜びや不安、明るさと暗さ、そして生と死といった対立物をひとつに抱えた存在で、そのどれもがおもしろい人間であると、総合的に認識できたのですから。
大人になること。
それは人生で自分にとって大事な問題をみつけて、信じる強さを持つことです。



































