映画配給会社リアリーライクフィルムズ代表・沖田敦さんに、今後の映画公開についてインタビューを敢行!
未曾有の世界的な課題である新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は、新作映画の公開に影響を与えています。アフターコロナ以後も、それ以前の興行スタイルで映画館に観客が戻ってくるのかという懸念を抱えています。
このような状態のなか、映画配給会社リアリーライクフィルムズの代表・沖田敦さんは、映画鑑賞の選択のひとつとして、現在、独自のオンラインシアターを継続して行なっています。

今回は「リビングルームシアター Living Room Theater」を立ち上げた、リアリーライクフィルムズ代表の沖田敦さんにネットで映画を鑑賞する意義や、配給事業を続けてきたからこそ、見出すことが出来た新たな可能性について、お話しをお伺いいたしました。
オンラインシアターの成り立ち
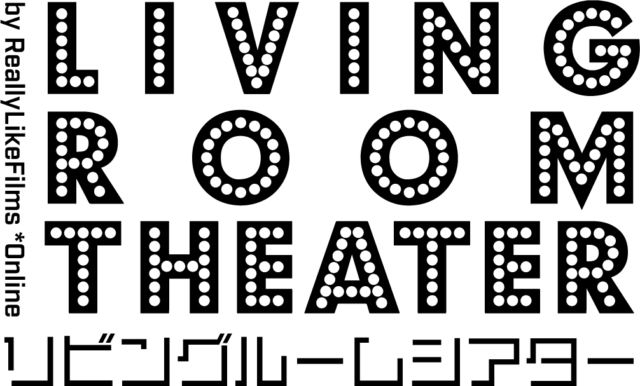
──今回リビングルームシアターという新たなオンラインシアターを立ち上げました。劇場での公開が厳しい状況の中、オンライン上の劇場を立ち上げようと思われたきっかけをお聞かせください。
沖田敦(以下、沖田):実はこの「オンラインシアター」の企画自体は、2014年頃に、映画館経営に興味がある投資家の方と知り合うことがあって、彼と話しているうちに、もっと自由に映画をみれる環境を提供することを目指した新しい映画館のコンセプトを思いついたんです。そのときに、「リビングルームシアター」という名前もあって…。
当時は、映画館のシステムが分からなかったので、映画館側の関係者何人かにお会いして、この企画の実施に向けた調整をしていきましたが、当時は誰からも理解を得られませんでした。それに映画館に係る投資規模はこの投資家と共有できていたのだけど、オンラインシアターのプラットフォームに思ったより経費が係る事がわかって、その投資家の気持ちが萎えてしまった。それで何となく話が立ち消えになっていたんです。
今回、コロナ禍による劇場の閉鎖の中、東風さんが「仮設の映画館」という期間限定のオンラインシアターを開設しようとしているという話を、イメージフォーラムの山下さんから教えていただいて、東風さんが既製のプラットフォームVimeoを利用して展開しようとしているということを知り、でも2014年当時はVimeoを利用してという発想が全くなくて、それなら自分にもできるんじゃないかと思ったんです。
──「Vimeo」自体は、数年前から普及していましたが、媒体として使うという流れになったのは、やはり今回のコロナ禍によるところが大きかったのでしょうか。
沖田:そうですね。まさにそこに合致したという感じです。2020年のコロナによる危機を逆に好機と捉えよう、と。そこで最初は「仮設の映画館」に参画する事も考えましたが、長期的に取り組みたいと思ったのです。
つまり、これまでの興行システムをなるべく維持していく。ただ今回はあくまで映画館が再開するまでの応急処置としての期間限定「オンラインシアター」を立ち上げるという発想になります。ですが、自分としては期間限定で、映画館の代替としてではなく、もうすこし幅を広げて永続的にやれるプラットフォームを作って行きたいと思ったのです。
映画館とネット配信の関わり
──ネット上での映画配給「リビングルームシアター」を立ち上げられた当初、映画館や映画配給会社との共生が前提にあったということですが、実際の映画館や映画配給会社との関わりについてどのように考えていますか。
沖田:通常、ある一定期間プロテクションを置いて、ビデオやテレビ・配信などの二次使用権を行使することという契約上の取り決めがあります。
今回は、映画公開と同時にオンラインシアターで公開するわけですから、日本側の興行サイドはもちろんですが、原権利者の理解を得ないといけない。そう言った大前提があるのですが、個人的には映画館に観に来る層と、スマホ、タブレット、デスクトップからテレビ、プロジェクターなど個人宅で映画を観る層とでは、異なっているという印象を持っています。もちろん平常時の話ですが。
僕たちの様にハリウッドやヨーロッパの大きな世界観の作品を観ている層にとっては、映画館で映画を観るという行為は日常からの完全な逸脱を意味していたので、特別な意味合いがあったと思います。しかし現代では興行収入の上位を占めるのは、若い俳優たちによって演じられるラブロマンスだったりコメディだったり、これは僕の勝手な印象かもしれませんが、日常の延長の中で等身大の登場人物たちが体験する、ちょっとした現実逃避の世界観があるんだと思います。テレビ番組を豪華な映画館で見ている様な感じ。それが今の人たちにとっては面白いんだろうと思います。
小林薫&西島秀俊共演『休暇』
プレミアロードショーにて配信中!
しかし、今回話しているのはそこじゃなくて、私たちの様なアートハウス系の作品について考えたかったのですが、世の中には、映画館を介さないで映画作品と出会う映画ファン層も一定数存在していると思います。その人たちは映画を観ることに執着していて、そのプラットフォームに固執しません。
それはいろんな理由があると思うのですが、家庭環境や仕事、身体的な理由。例えば僕個人のことで言えば、パニック障害の症状があるので、満席で通路側の席を取れなかったり、客席の足下の広さが異常に狭かったりすると、日によってはとても映画に集中できない精神状態になってしまう事があります。こんな仕事をしているのに、一番したい映画館に行く行為が恐怖に感じることさえあります。これは特別な例かもしれませんが、今回のコロナ渦の中では特に顕著にその動向が表出するのではないでしょうか。何が言いたいかっていうと、私たちにとって確かに映画館で映画を観てもらう事がファーストプライオリティーだけれども、映画を観ていただく環境はもう少しフレキシブルでいいのではないかという事です。
だから、今回、「リビングルームシアター」を通じて、映画館以外での「映画との出会い」に挑戦したかったのです。
──確かに本サイトCinemarcheでも、今回のコロナ禍がきっかけで、上映映画館よりも動画配信のほうが検索されるようになりました。それは大きな転換期を迎えたと実感しています。
沖田:映画に限らず、仕事や暮らし方など人々の価値観がコロナ以前とは大きく転換しています。その中で、映画作品との出会い方、映画との接し方も、変化していくわけで、既存の固定観念にとらわれないで、観客が視聴する環境を提案する時期に来ているように感じます。
映画館のあり方を問われる時代

──固定観念からの脱却ということですが、今後「withコロナ/アフターコロナ」と言われる新しい時代に、映画配給や映画館の在り方についてどのように考えていますか。
沖田:映画関係者には、映画館で鑑賞する人が減少し、今後、オンラインに大きく移行していくと予想する人もいるようですが、それはやはり極論だと思います。映画館はやっぱり大事です。作り手も最初から映画館で見せたいと思っている。だから作品づくりの前提として映画館で観られる場合を想定した画面作りがなされている。そういう作品は映画館で観られるのが筋だと思いますが、一方で、もっと他の選択肢があってもいいと考えてもいます。
先ほども少し触れましたが、観客の実態を考えるとどうか。「観る」という行為に対し、複数の選択肢がある。自分のライフスタイルと合っていない中で、映画と出会うためには映画館に行かねばならない、と強引に誘導される。それが観客にとっていいのだろうか。そして、今のマーケットと合っているのかどうか、ということを考えています。
今回のコロナの影響で、一時的に映画館離れになるかもしれない。でもオンラインでいろんな映画を観て、映画を観る慣習がついた人がまた映画館に戻ってくるように思います。まあ、僕は楽観的なのかもしれません(笑)。
コロナ禍とは関係なく考えていたこととして、現状、全国の映画館で毎週多種多様な映画が公開されています。週に何十本と新しい映画が公開されています。その映画作品を何カ月後かにオンラインで放映しても、優れた作品だけれど大々的な話題にはならなかったものには、やはり関心がいかない。
それが、劇場公開時にオンラインで同時に公開する。そのことで観客にとってそれぞれが観やすい環境を選択できることが、映画界全体の裾野が拡がると確信しています。「劇場に行くのはコロナが心配だけど、オンラインだったら観れるな」とか、「子どもがいて手が放せないけど、オンラインだったら夜中に1人で視聴できる」とか。何かそういう選択肢があるほうがいいと思うんです。
デビッド・ロバート・ミッチェル監督作品『アメリカン・スリープオーバー』
シネマテークにて配信中!
──そのためにも、映画館とオンラインとの共生が課題になる。
沖田:最悪のシナリオは、オンラインだけで事が足りてしまって、映画館で観るって行為自体が廃れていく…。
──その入れ替わった結果、どちらかが滅んでしまうことを一番避けたいと思います。
沖田:「共生」を目指すためにも、映画館の協力が不可欠です。個々の映画館の存続だけを目指すのか、オンラインとの共生を目指すために、映画館にオンラインでの売り上げをなんらかの形で還元するようなシステムを構築し検証するのか、その可否を含めて映画作品、映画館の価値観が問われているのだと思います。
配給で選ぶという新たな楽しみ方
角田龍一監督作作品『血筋』
架空映画館にて配信中!
──そうですね。映画の業界全体を守るためでもあるし、一方で、観客の多様なニーズに対応するための選択肢を増やしたり、また作り手の思いを達成できるものだったり、今回の「リビングルームシアター」は、かなり画期的だと感じてはいます。そこで「リビングルームシアター」ならではの、映画の楽しみ方はありますか。
沖田:他のオンラインシアターとは異なる楽しみ方として、現在のところ三つのチャンネル分けをしているところかもしれません。映画館の公開と同時配信する《架空映画館》、映画館の公開は終えたけれども他では観れない独占配信作品、またはESTのみのVOD作品に限定して配信する《プレミアロードショー》、それ以外のアーカイブ作品を配信する《シネマテーク》の3つです。
さらに各サイトには弊社だけではなく、キュレーションシステムをとっていて、現在は三名の方にご協力いただいています。『血筋』『フェイクプラスティックプラネット』『アイたちのいる学校』のアルミードさん、『休暇』『ホーム・スィートホーム』などのシネマエンジェルさん、『世界で一番ゴッホを描いた』『アメリカン・スリーブオーバー』のシンブルプラスさんです。シンプルプラスの祖山代表は、実は2014年当初からお力添えをいただいていた方で、今回大きなサポートをしていただいています。単純に無作為に作品を配信するのではなく、こうした作品を提供している方たちの審美眼も同時に感じていただけるところも、映画の楽しみ方の手順となって楽しんでいただけると思います。
ユイ・ハイボー&キキ・ティンチー・ユイ監督作品
『世界で一番ゴッホを描いた』シネマテークにて配信中!
このキュレーターではないですけど、ミニシアター全盛期には、例えばフランス映画社やシネセゾンという配給会社に一定数のファンがついていたと思います。フランス映画社が選んできた映画だからというだけで、映画ファンの絶対的な信頼を勝ち取っていました。現在、アメリカでは「A24」という映画会社が、会社としてのブランディングを確立させています。その配給会社なら観に行こうというお客様がかなりいるのです。
一方で日本の大半の映画ファンは、映画館に作品のイメージを定着させる傾向にあります。かつてのミニシアターが外国映画を上映する場所として認知されていたのに対して、一部の旗艦館を除くと、現在はむしろ邦画のインディーズを紹介するところだという認識が強いのではないでしょうか? しかもシネコンと同じで、多種多様な作品を同時期に一編に公開しているといったイメージです。そこに新しく配給会社という基準があっても面白いんじゃないか。今の時代、むしろインディーズ系の配給会社の方が個性的でセレクティブな存在なのではないでしょうか? まさにキュレーションしている人のセンスで観るという選択肢です。
配給という仕事

──今回「リビングルームシアター」の開設によって、新しい映画配給の形が「リビングルームシアター」で展開されました。沖田さんは日活での映画宣伝部以降、映画配給に長らく携わってきましたが、ご自身にとって配給の仕事のやりがいなどお聞かせください。
沖田:私の配給会社では外国映画を扱っており、海外の新しい才能、素晴らしい作品と出会い、それを日本に紹介する仕事だと思っています。自分が見つけた才能、新鮮な作品を、興行会社と共有し、映画館にかけてもらう。そして、映画館が決まったら、メディアに対して、その自分が買ってきた作品をプロモートし、興味を持ってくれたジャーナリストや媒体の方達が、それぞれの言葉で作品をメディアを通して伝えてくれる、そして買付から短くて1年、長ければ2年の時を経て映画公開まで漕ぎ着ける。
自分が買い付けてから、作品の公開までの間のこれらの工程、そのものが僕には何にも変え難い悦びなんです。それはオンラインシアターで公開する事も、僕にとっては大差はありません。オンラインにチックインして、それがリアルタイムでメールでレポートが来る。お客様のお顔は拝見できませんが、映画館でお客様をお待ちしている時と同じくらいの悦びを感じる事ができます。
編集部:今まで配給した作品で、印象深い作品はありますか。
沖田:それはパトリス・ルコント監督作品ですね。僕が買い付けした作品ではありませんが、僕が独立するまで在籍していた会社の時に、当時の専務が買い付けてきた作品が『髪結いの亭主』でした。このとき、その会社は経営が悪化していて代表は契約をキャンセルしようとしていました。
当時映画事業に関わっていたのは僕を含め4人いたのですが、現場のみんなで結託して頑としてキャンセルすることを拒みました。その時に同僚の女性、後に彼女と僕は独立して一緒に配給会社を立ち上げることになるのですが、彼女が友人が務めていた某テレビ局に相談を持ちかけて、ここからの出資を取り付けたんです。当時この局は『恋のゆくえ/ファビラス・ベイカー・ボーイズ』を公開しようとしていて、でも『髪結の亭主』のような純然たる単館作品には出資事例がなかったので、特別な決定だったと思います。
これで社長を説得してなんとかキャンセルを思いとどませた。今考えると映画事業の撤退を考えていた代表が、僕たちの給与を含めた固定費をずっと負担してくれていたわけですから、本当にろくでもない社員だったと思います。でもこの映画の成功のおかげで、その配給会社は業界でも一目置かれる存在になったと思います。
それ以降、パトリス・ルコント監督とは交流が続き、独立後もその関係は継続していきました。いい時も悪い時も僕たちは彼と共に在った訳で、それは言葉では表現し難い特別な感情があります。
今後の展望ー新しい世界に向けて
カテル・キレベレ監督作『あさがくるまえに』
シネマテークにて配信中!
──2020年は映画の存在自体を揺るがす状態が訪れた年になりました。だからこそこれまでとは違う形で、映画の新しい出会い方、楽しみ方を提示できたと感じています。
沖田:先ほどは楽観的な意見を述べましたが、正直どうなるかはわかりません。映画館に行かなくなるのか、みんなパソコンやテレビ、オンラインコンテンツにシフトしていくのか。今後様子を見ながら、柔軟に対応していきたいです。
現在、以前よりも映画の制作側は、作りやすくなってきています。より多くの映画が作られていますが、逆に精査し、配給宣伝の役割として観客の皆さんに伝えていく。そうしないと、いくら映画好きであっても、その作品量に圧倒され、しかもピンからキリまであって、面白い作品に出会う前に、何を見てもいいか分からなくなっている。
理想として、「リビングルームシアター」に来れば、自分の好みに合った映画が並んでいるな、この映画配給会社の作品なら観たいという形で、浸透していけるようにしたいです。
沖田敦さんのプロフィール

にっかつ(現日活)洋画宣伝部、アルシネテランを経て、1997年にフランス映画に特化した配給会社ワイズポリシー(元シネマパリジャン)を立ち上げ、『橋の上の娘』(LANCOM presents)、『クリクリのいた夏』(Hermes Presents)、『ドライ・クリーニング』、『ディナーラッシュ』、『Water』、『LIVE FOREVER』、『タロットカード殺人事件』、『プロークバック・マウンテン』『ラスト、コーション/色・戒』など、いづれも興行的に大きな成功を収めた。
2014年にワン・ツー・サンシャインフィルムのアドバイザー、株式会社ヘブンキャンウエイトのプロデューサーなどを経て、現在はリアリーライクフィルムズ合同会社の代表社員に就いている。
【主な手掛けた作品】
『なまいきシャルロット』『バットテイスト』『オープニングナイト』『髪結いの亭主』『タンゴ』『マッチ工場の少女』『ハモンハモン』『パリ空港の人々』『リディキュール』『ハーフアチャンス』『橋の上の娘』『バッドサンタ』『ピエロの赤い鼻』『あさがくるまえに』他、100作品以上。











































